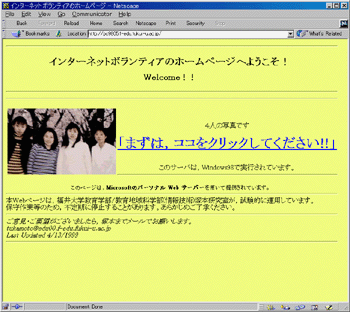
図1 インターネットボランティアのホームページ
活動者/語り手:中合幸恵・圓道敦子・齊藤恵・櫻谷朋子,監修:塚本 充
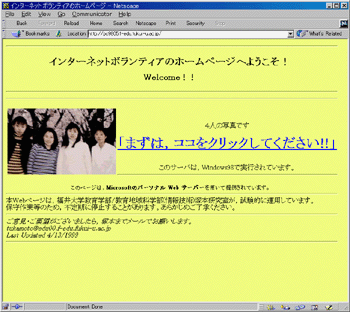
私たちが所属するコースでは,3年次になるときに研究室配属が決まります。私たちが配属されることになった研究室は,年中行事(?)として8月上旬の「大学説明会」や秋に開催される「オープンキャンパス福大」に企画を出して参加しています。今年は,さらにインターネットボランティアの活動が行事に加わることになりました。
私たちに,インターネットボランティアの話があったのは,行事の一つであるオープンキャンパスの当日でした。指導教官が「インターネットボランティアの募集への御協力のお願い」という教育学部附属養護学校長名の文書を見せて,協力を依頼されました。内容の項目に「ア.本校の教育や児童・生徒を理解してくれる大学生と電子メールの交換,インターネット電話,CU-SeeMeによる簡単なテレビ会議等のオンライン交流とともにオフライン(本校で直接,会って話をする)交流を加えてより深い交流を図る。うんぬん...」「イ.(可能であれば)知的発達障害児にとって必要な情報を考え,わかりやすいホームページを作成していただきたい」とありました。要するに養護学校の生徒とメールのやりとりをしたり,ホームページを作ったりすればいいわけねと内心楽勝だと皆そう思いました。具体的な活動日程などの詳細は,養護学校の担当の先生に尋ねてほしいといういうことでした。
後期が始まって、インターネットボランティアのことなど,完璧に忘れて勉学に没頭していた頃,養護学校の担当先生からのFAXと電子メールのコピーを指導教官から受け取りました。「できれば早いうちに学生さんと直接会ってお話をしたいと思います」とありました。また,電子メールの文面より,
・養護学校の生徒は、高等部女子でパソコンクラブの部員4名であること。
・この活動は,100校プロジェクトの一環として企画された実験的要素があるということ。
などがわかりました。10月の末,心はすでに11月の連休にある日の午後でした。
その後,養護学校の先生と生徒に何度か会うことになりました。ホームページ作成やNetMeetingをおこなうパソコンをいかにして調達するかなども話題になりました。教育実践研究指導センターのパソコンを使わせていただくということも検討しましたが,不特定多数のものが利用するため難しいことがわかりました。結局、私たちの研究室で授業用に利用されているパソコンをWebサーバに仕立てることになりました。実際の作業は,私たちの手に負えるものではなく,すべて指導教官にやっていただきました。内蔵ハードディスクを3.5GBのものに換装し,メモリをほかのパソコンからはぎ取って増設したとのことです。マザーボードのクロック周波数を50MHzから66MHzにアップしようか,まぁWebサーバなら,Pentium-75Mhzで十分でしょうとのことでした。さらに,Windows95上で稼働するパーソナルWebサーバをインストール,設定してもらいました。そして,簡単なWebページの雛形を用意してもらい,あとは,養護学校の先生にお借りしたデジタルカメラで撮影した画像をパソコンに取り込んだり,ペイントブラシで描いた絵をページに貼り込む作業をしました。Webページ作成支援ソフトを使わずに,HTMLを記述するためにWindows標準アプリケーションであるメモ帳を用いました。
年末年始の休みが終わって,正月ぼけが直りきらない頃,養護学校の担当の先生からWebページを完成させてほしいという依頼のメールが届いていることが判明しました。完成の期限は,12月の末!?12月の半ばに授業期間が終わって,それ以来大学から足が遠退いていたため,メールのチェックをしていなかったのでした。それからは,毎日がWebページ作成の日々でした。はじめのうちは,タグを調べながら記述していたHTMLも,いちいち調べずに書けるようになりました。そして,ついに「手づくりかみしばい」をはじめとする約60ページにも及ぶ作品ができあがりました。ファイル容量は,テキストと画像データの合計で約1.7MBにもなりました。図2に「手づくりかみしばい」の最初の4ページを示します。
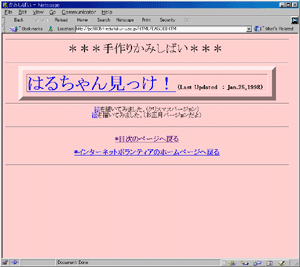
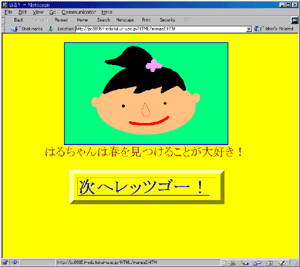
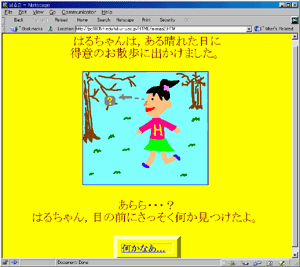
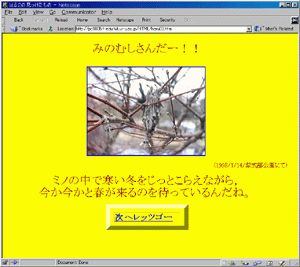
「手作りかみしばい」は養護学校の児童・生徒にとっても,読みやすいように「ひらがなバージョン」も用意しました。私たちが作成したWebページには,それ以外にも,養護学校の生徒が興味を持つような内容をふんだんに取り入れるなど工夫を凝らしたつもりです。「ふだんの私たちの生活」を紹介したページの中の「お天気のいい日は」の項目のページを図3に示します。また,生徒たちが興味を持っていることがらをあらかじめ聞いておきましたので,その項目へのリンクのページも用意しました(図4)。

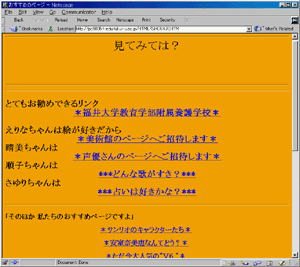
2月12日夕刻,私たちは,はじめてNetMeetingを体験しました。養護学校の生徒の声が研究室のパソコンのスピーカから聞こえたときは興奮しました。双方でインターネットボランティアのホームページを閲覧しながら,「○○ちゃんの好きなタレントのホームページを探しておいたよ」などいろいろな話で盛り上がってしまいました。このような,メールやWWWとちがったインターネットの使い方に触れることができたことは貴重な体験です。そして,なにより養護学校の生徒たちとの交流の機会を持てたこのインターネットボランティアの活動に参加できてよかったと思っています。
なお,インターネットボランティアのURLは,「http://pc9805.f-edu.fukui-u.ac.jp/」です。よろしければ,のぞいてみてください。
本稿では,インターネットボランティアの体験の一部を紹介しました。また,いつか一連の活動の詳細や後日談を報告できる機会があれば,お話ししたいと思います。
(なかごうゆきえ:教育学部情報社会文化課程3年)
(えんどうあつこ:教育学部情報社会文化課程3年)
(さいとう けい:教育学部情報社会文化課程3年)
(さくらやともこ:教育学部情報社会文化課程3年)
(つかもとみつる:教育学部情報技術・センター兼任)